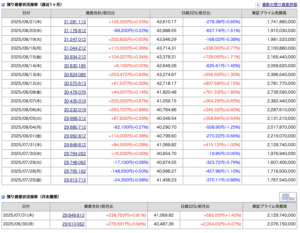皆さんお疲れ様です。
最近話題の中田敦彦さんのYouTube動画、「国債で減税していいのか?」を拝見しました。
どんな内容かというと要は国債を刷って減税するのではなく、法人税等溜め込んでるところから取りなさいよって話でした。
動画の中で気になった点をいくつか掘り下げたいと思います。
ニクソン・ショックによって、米ドルは金との兌換性を失いました。これは、それまでドルが金と交換できる「兌換紙幣」であった状態から、「不換紙幣」に移行したことを意味します。しかし、ドルが基軸通貨としての地位を維持できた背景には、「ペトロダラーシステム」の構築が大きく影響しています。
ペトロダラーシステムとは?
1970年代に入ると、アメリカはサウジアラビアをはじめとする主要産油国と合意を結びました。この合意の要点は以下の通りです。
- 原油取引のドル建て決済: OPEC(石油輸出国機構)加盟国は、原油の輸出代金を米ドルで受け取ることを原則としました。
- 米国の軍事支援と保護: 見返りとして、アメリカは産油国に対して軍事的な保護を提供しました。
これにより、世界中の国が原油を購入するためにドルを必要とするようになり、原油の取引市場でドルの需要が確保されました。これが、ドルが「金と交換できない紙幣」から「原油と交換できる紙幣」になったと言われる理由です。現在も、国際的な原油取引の多くはドル建てで行われています。
中東情勢と米国の関与
アメリカが中東地域に深く関与してきた理由の一つに、このペトロダラーシステムを維持し、ドルの基軸通貨としての地位を守るという目的があったと指摘されることがあります。原油の安定供給と、その取引におけるドルの優位性を確保することは、米国の経済的な国益にとって非常に重要でした。
やはり、アベノミクス下での株価上昇は、日本銀行による大規模な金融緩和策が大きな要因として挙げられます。
具体的には、以下の2つの政策が市場に強い影響を与えました。
- ETF(上場投資信託)の買い入れ: 日銀が直接的に株式市場のETFを購入したことは、株価を下支えし、市場全体の株価上昇に直接的な効果をもたらしました。特定の銘柄(例えば、値がさ株など)が買い入れの対象となることで、その株価が実態以上に押し上げられたという見方もあります。
- イールドカーブコントロール(長短金利操作): 長期金利を低く抑えるこの政策は、銀行や生命保険会社のような機関投資家の運用環境を大きく変えました。それまで収益の柱だった国債での運用が難しくなったため、より高い利回りを求めて資金が株式市場へと流入しました。この資金シフトが、株価をさらに押し上げる要因となりました。
円安も株価に影響を与えますが、これは主に輸出企業の業績を通じて間接的に作用します。円安が進むと、海外での売り上げが円換算で増え、企業の利益が向上します。その結果、企業業績への期待から株価が上昇します。しかし、アベノミクス期間中に見られた株価の急激な上昇には、日銀による直接的・間接的な資金供給という、より強い推進力があったと考えるのが一般的です。
どちらの要因も株価に影響を与えましたが、その影響力の大きさを比較した場合、日銀の金融緩和策がより直接的で強力な要因であったと言えるでしょう。
賃上げが進まなかった理由について
日本の就職氷河期と賃上げの背景
日本の就職氷河期には、いくつかの要因が絡み合っています。一時的に企業に余剰人員が出ていたことや、内需主導の経済構造が背景にあるのは事実です。
しかし、私が考える最も大きな理由は年金制度です。団塊の世代の年金支給開始年齢を先送りした結果、本来定年退職するはずだった多くの人々が企業に残りました。企業は人件費の観点から新卒採用を抑える傾向にありました。いくら若い世代を育成する意図があったとしても、経験豊富なベテラン社員の方が即戦力として評価され、結果的に新卒採用が見送られたと考えられます。
最近になって賃上げが進んでいるのは、この状況が正常化し、さらに若い世代の人口減少が進んでいるためです。企業は限られた人材を確保するために、賃金を引き上げる必要に迫られています。
世界経済と日本の現状
また、現在のインフレはコストプッシュ型インフレの影響も無視できません。日本が経済的に停滞していた間、世界は急速に豊かさを求め、実際に発展しました。食料や燃料など、以前は一部の先進国が独占していた資源が、新興国の需要増加によって価格が上昇しています。
これは、世界全体で豊かさの底上げが起こっている証拠であり、日本もその国際的な経済動向の影響を強く受けているのです。
国債を大量に発行することで、政府は一時的に税収を増やすことなく財源を確保できます。しかし、その結果として通貨の供給量が増えすぎると、インフレーション(物価の上昇)が引き起こされます。これにより、お金の購買力が低下し、国民の実質的な資産価値が減少します。この現象はインフレ税と呼ばれ、実質的に国民から税金を徴収しているのと同等の効果を持ちます。
もう一つの疑問として、町内会費やサークルの会費が定額である一方、税金が所得に応じて変動する(累進課税)のは不公平ではないか、という点があります。これは、現代の資本主義社会が抱える格差拡大という問題を是正するためです。経済学者トマ・ピケティが提唱した**(資本収益率が経済成長率を上回る)**という現象が示すように、資本家が持つ資産は労働による所得よりも速いペースで増える傾向にあります。この格差を放置すると、貧富の差はさらに拡大してしまいます。
そのため、税金、特に累進課税は、所得や富がより大きい人々から多くの税を徴収し、公共サービスを通じて社会全体に再分配する機能を持っています。これは、単にお金を再分配するだけでなく、社会全体の安定と持続可能な成長を維持するために不可欠な仕組みです。
そうした観点から法人税の引き上げは、理論的には富の再分配の一環として妥当に見えます。しかし、現在の日本の経済状況を鑑みると、法人税の引き上げは企業の投資意欲や競争力を低下させ、景気回復の足かせとなるリスクも伴います。特に、個人投資家がNISAなどを通じて投資を始めている中で、法人税の引き上げが企業収益の減少につながれば、株価にも悪影響を与える可能性は高いでしょう。
まとめ
以上が私が動画を見た感想です。私に直接会える人限定になってしまいますがご意見ください。